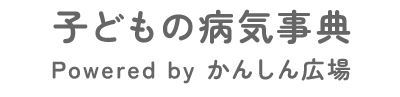有機酸代謝異常症とは

有機酸代謝異常症は、有機酸代謝に必要な酵素が生まれつきうまく働かないために、体の中に様々な有機酸が蓄積して急性および慢性の障害を引き起こす先天性異常症です。
そもそも有機酸とは、炭素を含む化合物のことで、炭化水素骨格の短いカルボン酸 (-COOH) を指します。
有機酸は、食べ物の中に含まれているたんぱく質や脂肪の一部が分解される過程で生じます。特にたんぱく質がアミノ酸に分解され、さらにアミノ酸のアミノ基(-NH2など)が外れたものが有機酸の大部分を占めます。この有機酸を分解する酵素が欠損し、代謝がせき止められて体の中に溜まってしまう疾患が有機酸代謝異常症です。
主な有機酸代謝異常症は以下の通りです。
- メチルマロン酸血症
- プロピオン酸血症
- イソ吉草酸血症
- メチルクロトニルグリシン尿症
- 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタル酸血症
- 複合カルボキシラーゼ欠損症
- グルタル酸血症Ⅰ型
- βケトチオラーゼ欠損症
これらの有機酸代謝異常症は、出生後早期に発見して適切な治療を開始することで、急性症状を防いで良好な成長や発達につなげることができます。そのため、日本では新生児マススクリーニング検査の対象疾患です。また、小児慢性特定疾病に指定されており、一部の疾患は指定難病にも指定されています。
有機酸代謝異常症の症状
有機酸代謝異常症は、体にとって有害な「酸」が蓄積することで、体が酸性(アシドーシス)に傾いてさまざまな症状があらわれます。新生児マススクリーニングをすり抜けた例で、無治療で経過した場合、重症度ごとの症状の特徴は以下の通りです。
軽症例
乳幼児期以降に嘔吐を繰り返したり、離乳食が進まず発育が遅くなったり、徐々に発達が遅れたりするなどの症状から受診をし、詳しい検査をして見つかることがあります。
重症例
特に乳児ではミルクや母乳の飲みが悪くなる、嘔吐、うとうとするような傾眠などの症状がみられます。診断が確定して治療中の児でも、感染症罹患時などに代謝異常が進行し、意識がなくなって昏睡状態になってけいれんを引き起こす場合もあります。これは、代謝性アシドーシスや高アンモニア血症などによるものです。また、治療が遅れると短時間のうちに命を落とすこともあるため、早期発見と適切な治療が必要です。
有機酸代謝異常症の検査方法

有機酸代謝異常症は、血液検査と尿検査を行います。
血液検査では以下の項目を確認しています。
● 新生児マススクリーニングの結果
● 血液ガス分析
● 電解質
● 血糖値
● アンモニア値
● 血中乳酸/ピルビン酸
● 血中/尿中ケトン体
など
発症後であっても、新生児マススクリーニング陽性で発症前であっても、血液検査では代謝性アシドーシスや高アンモニア血症の有無を確認するとともに、肝機能や腎機能も評価します。有機酸代謝異常症を疑った場合は、尿の中に有機酸が含まれていないかを調べるために尿中有機酸分析を行います。また、血液を用いたタンデムマス分析(新生児マススクリーニングと同じ検査)も行います。新生児マススクリーニングは濾紙血というものを用いますが、血清を用いて検査を行うことも有用です。
これらの検査から有機酸代謝異常症が疑われるときは、確定診断のために遺伝子検査を行います。
有機酸代謝異常症の治療法

有機酸代謝異常症は子どもの頃から治療と予防が必要です。有機酸代謝異常症の基本的な治療の考え方は、アミノ酸代謝異常症と同じく蓄積する有機酸の元となるアミノ酸を制限することです。つまりタンパク質の摂取量を制限することが大切です。それと共に、必要な摂取カロリーを確保することも重要です。
有機酸代謝異常症の治療は急性期に対する治療と安定期に継続して行う治療に分けられます。
急性期の治療
嘔吐や意識障害、けいれんなどの症状があるときは、入院してすぐに十分なブドウ糖を点滴することでアミノ酸が血液中に増加するのを抑制します。医師の指示があるまでは、食事からのタンパク質の摂取は控えましょう。
病型によってはビタミン類の投与が効果を示すことが分かっています。蓄積した有機物の排泄を促すカルニチンの投与が有効です。
安定期の治療
アシドーシスが改善している安定期は急性症状の再燃を予防し、成長・発達への悪影響を防ぐのが目的です。症状や検査値を確認しながら、タンパク質やアミノ酸の摂取制限をしたり、カルニチンやビタミンB12などのビタミン剤の摂取を続けます。
子どもの場合、乳児期にはたんぱく質を除去した上で、制限対象以外のアミノ酸の混合物を加えた「治療用ミルク」を使用し、カロリーを確保します。離乳食以降は、食品の特定のアミノ酸を取り除くことはできないため、アミノ酸の摂取量を制限しながら食事管理を行います。その場合、成人してからも「治療用ミルク」を使用することがあります。
疾患によっては、完治を目指せるわけではありませんが、症状を軽くするのに肝移植が有効です。将来的に腎不全が進行し、腎移植が必要になることもあります。
まとめ
有機酸代謝異常症は新生児マススクリーニング検査の対象疾患になっている先天性代謝異常です。有機酸代謝異常症は現時点では根治療法がなく、有機酸が蓄積しないように、食事療法や薬物療法を継続することが必要です。特に子どもは症状を上手く伝えられないため、治療中であっても、気になる症状があれば、すぐに医療機関を受診しましょう。
監修医:国立研究開発法人 国立成育医療センター 総合診療部 統括部長 窪田満 先生
参考文献
https://www.jsms.gr.jp/download/guidebook_b.pdf
https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/040.html
https://jsimd.net/documents/GuidelinesInClinicalGenetics/yuukisantaisyaijousyou.pdf
https://hidamari-tanpopo.main.jp/fatty-acid-oxidation.html
https://kobe-kishida-clinic.com/metabolism/metabolic-disorder/disorders-of-organic-acid-metabolism/#:~:text=%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BD%93%E8%87%AD-,%E8%A1%80%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%A8%E5%B0%BF%E6%A4%9C%E6%9F%BB,%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82